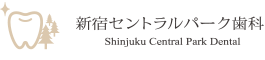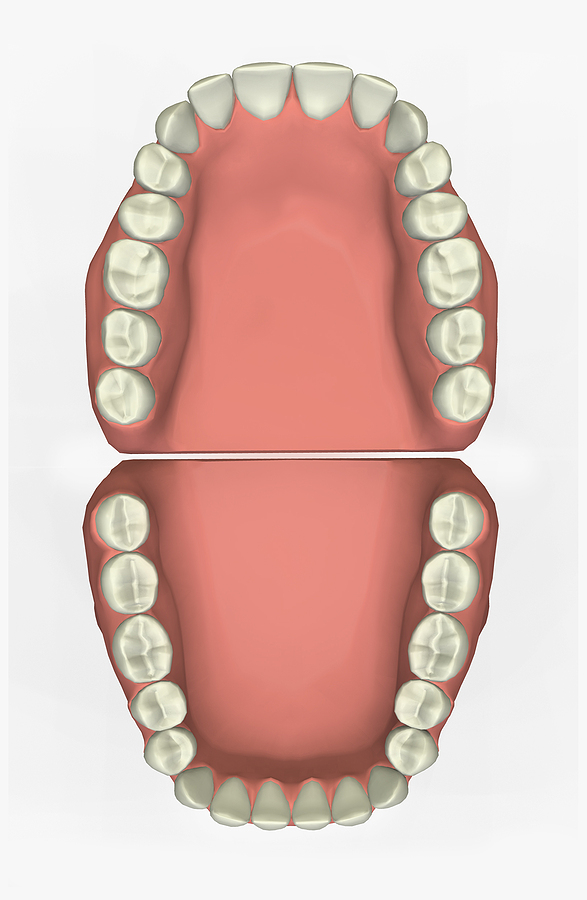酸蝕症(さんしょくしょう)とは?
酸蝕症とは、酸によって歯の表面(エナメル質)が溶けてしまう病気のことです。
むし歯は虫歯菌が酸を出すことで歯を溶かしますが、酸蝕症は飲食物や胃酸など、外からの酸の影響で歯が直接ダメージを受ける点が特徴です。
酸蝕症の原因
-
飲食物による酸
炭酸飲料、スポーツドリンク、ワイン、柑橘類などを頻繁に摂取するとリスクが高まります。 -
胃酸の逆流
逆流性食道炎や嘔吐を繰り返す習慣がある場合、強い酸で歯が溶けてしまいます。 -
生活習慣
長時間飲み続ける「ダラダラ飲み」や、就寝前の酸性飲料摂取も大きな要因です。
酸蝕症の症状
-
歯が透けて見える
-
表面がツルツルしている
-
冷たいものや甘いものがしみる
-
黄ばんで見える
-
歯がすり減って短く見える
酸蝕症の治療方法
酸蝕症は、進行度によって治療の選択肢が変わります。
-
初期段階(軽度)
-
フッ素塗布で歯を強化
-
専用の歯磨き粉で再石灰化を促進
-
生活習慣の改善(酸性飲料のコントロールなど)
-
-
中等度(歯の形が変わり始めている場合)
-
コンポジットレジン修復(白い詰め物で欠けやすり減りを補う)
-
ラミネートベニア(薄いセラミックシェルを前歯の表面に貼り付け、色や形を回復する)
-
-
重度(歯が大きく失われている場合)
-
**セラミッククラウン(被せ物)**で歯の全体を保護
-
奥歯では、咬耗を補正するクラウンで噛み合わせを回復
-
ベニア治療のメリット
特に前歯の酸蝕症においては、ラミネートベニアが有効です。
-
自然な白さと透明感を再現できる
-
歯の表面を守り、しみやすさを軽減できる
-
形や長さを整えて審美的にも改善できる
まとめ
酸蝕症は生活習慣や全身の状態と深く関係しており、進行すると歯が弱くなり見た目や機能に影響します。
フッ素やレジンでの初期対応から、ベニアやクラウンによる修復まで、状態に応じた治療が可能です。
「歯が透けて見える」「黄ばみが気になる」といった症状があれば、早めに当院で相談し、自分に合った治療法を選びましょう。